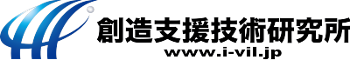■「情報リテラシー」について
「情報リテラシー」という言葉は、ビジネスにかかわる方はもとより学生の方でも多くの人が一度は耳にしたことがあると思います。
しかしながら、言葉は聞いたことがあっても、その内容の理解となると、人により大きな差があるのではないかと感じています。
さらに、正しく身につけていると自信をもって言える人となると、極わずかなのではないか? と思います。
このような状況は、昨今のように急激に進展している現在の情報化社会では、早急に改善しなければいけない問題です。
なぜかといいますと、情報リテラシーは情報化社会で生活する上での「土台、基盤(インフラ)」となるもののひとつだからです。ところが情報リテラシーは目に見えるものではありませんし、それを身につけているか否かを日常生活で問われることはまず無いので、多くの人にとってはあまり重要とは感じにくいのでしょう。
私は、情報リテラシーをきちんと身につけることを軽視して、情報機器やソフトウェア、その他環境など単に上ものばかりの進歩ばかり注目しているような状況が続くと、場合によっては社会生活全てを崩壊させてしまう危険があると考えています。
そこで、情報リテラシーを今一度考え直すためのきっかけをお話したく思いました。
まず「リテラシー」についてですが、これ自体は一般に「基本的な教養」のことをさすということは多くの方がご承知のとおりです。ちなみに、「リテラシー」=「読み・書き・ソロバン」と解釈されている人もいますが、それだけではありません。あくまで「教養」全般です。(さらに、「教養」は単に知識だけをさすものではなく、それ(知識)を「使いこなすこと、力」も含まれる・・・ということについては、また、別の機会にお話します。)
ならば「情報リテラシー」となりますと「情報に関する基本的な教養」となるのでしょうが、具体的にどういうものを指し、何をどこまで身につけていれば良いのかということについては明確になっておらず、私の周りの人を見る限りでは「身につけていますよ」と言う人でも、間違った理解をしている人が多いと感じています。
「情報リテラシーを身につけたくたって技術の進歩が早いから追いつけない!」とか「時代によって変わるんでしょ?」などということを言う人もいます。 が、それこそ間違って解釈している人の証拠なのです。
たしかに「何をどこまで身につければ良いか」ということについては、個々の人の置かれた立場にもよりますし、一概に定義することは難しいところです。
しかしながらリテラシーというものは前記のようにインフラですからある意味「共通のベース」になるものであり、その性質は基本的には普遍的なものです。ですから「どこまで…」という深さに多少の違いはあるものの、その人の置かれた環境や時代が変化しても身につけておくべきポイント自体はさほど違わないものなのです。
もちろんその時代におけるパラダイムシフトなどの影響を受けて、多少変化することもあるでしょう。しかし情報リテラシーは具体的な技術そのもののことを指すわけではないので、急に変化してしまうといったものでは無いのです。
さて、ではそもそも「情報」とは何でしょうか?
具体的に定義しようとしても非常に多くの内容を含み、広範に及ぶものなので一言で言い表すことは難しいのですが、抽象的になってしまうこと承知の上で私の考えるところを述べますと、「それをあらわすもの。つたえるなど、やり取りをするもの。自身を含みあらゆるものを生み出すための原資となるもの。自身や他(周囲の環境)に何らかの影響を与えるもの。」などとなり、また、少し哲学的になりますが「すべてのものが持っているもの」とも言えると思っています。(以下、この考えに従って定義したものを【情報】と表記します)
そこで「情報リテラシー」とは何かを今一度考えて見ますと、
「【情報】とはなにかということ、また【情報】の性質、役割はなにかということを正しく理解し、正しく取り扱うための教養」と言えると思います。
今の時代、年齢、職業に関係なく、すべての人は情報に関わらずに過ごすができないことは言うまでもありません。
ですから、たとえば「私は適切に情報を扱うことができる」と言えるようになるためには、きちんと情報リテラシーを身につけることが要求されるのです。
そこで一念発起し自分で勉強しようと思って本屋さんに行くと、「◯◯で身につける情報リテラシー」などといったタイトルの本があり、その内容はというと文書作成ソフトや表計算ソフト、プレゼン資料作成ソフトなど、オフィスユースのソフトウェアツールの説明や解説であるものが多く並べられているのが現状です。私はそのような本を見ると「ちょっと違うんじゃないかな?」と言いたくなります。
「オフィスソフトの使い方を習得すること」=「情報リテラシーを身につけること」のように考えられていることが、多くのビジネスマン、ビジネスウーマンの中に「私はすでに十分に身につけている」と誤解している人がいることと関係があるかもしれません。
こうした誤解をした状態は非常に危険です。情報リテラシーを誤解している人は自分では正しく理解しているつもりになっているだけですから、実際には【情報】の適切な取り扱い方法が身についてはいない人ということになります。そのような人は重大な「事故」を発生させてしまう可能性を持った人とも言えます(ちょっと、言い過ぎですが…)。
たとえばオフィスソフトの使い方を身につけただけで、【情報】の適切な取扱い方法は身についていなかったとします。すると、安易な保管方法や、他者とのやりとりをして重要な【情報】が他人に渡してしまいかねません。さらに、悪意ある人の不適切な行為に気づかず、その結果その【情報】が悪用されてしまうことも考えられます。そうなったら何が起きるでしょうか?
説明するまでもありません。新聞紙上を賑わせているような「事件・事故」に繋がってしまうのです。企業ならば倒産、個人ならば生活破綻、家庭崩壊、お金にかかわることから命にかかわる問題まで、人生を暗転させ、さらには取り返しのつかないことにまで発展させてしまうリスクがあるのです。
もちろん世の中には完全ということはありません。避けられない事故もあるでしょう。
しかし正しく【情報】を理解し、適切に管理し取り扱っていれば、無用な人に不用意に重要な【情報】が渡されたり使われたりするリスクを減らすことはできます。ですから適切に【情報】というものを理解し、どのように扱い管理・使用することが必要かを理解しておくこと、つまり「情報リテラシーを適切に身につけておくこと」が重要になるのです。
今一度、自分がどのように【情報】を取り扱っているか、冷静に現実を見てみましょう。
ここのところ新聞やニュースで情報に関連した事件・事故のアナウンスが後を絶ちません。こうした情報に関連した事件・事故は、一見「悪意をもった人が犯した犯罪」のように見えます。たしかにそうしたケースもあります。しかし実際には情報リテラシーの欠如に起因し、適切な【情報】の取扱いや管理ができていなかったことが原因であることの方が多いのです。
少し長くなってしまいましたが、ここまで、情報リテラシーをもう一度考えるきっかけ作りにつなげる話題として、情報リテラシーの欠如とそれに起因して発生する「事故」などについてお話しました。
では、「情報リテラシーをどのようにして身につけて行ったら良いか」ということになるのですが、この続きは後日また掲載します。
今回は「きっかけ作り」を目的として述べてまいりました。
皆様のご意見、ご感想をお待ちしております。